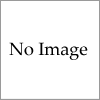
第1章はAssociational Cognition(連帯認知)のシステムとしての「企業」の導入。第2章ではAssociational Cognition(連帯認知)とOrganizational Architecture(組織構造)、Corporate Governance(企業統治)との関係を整理。第3章では企業活動をゲーム理論を使い政治的・社会的側面から分析し、政治制度の枠組み、社会的規範の役割、また政治・社会・企業間の相互帰還関係について洞察。第4章では社会ゲームのルールの進化について複雑系の視点を再確認。第5章は現在進行中の企業構造の多様化について日本企業の分析を中心に掘り下げています。青木昌彦教授の著書は初めてですが目から鱗が落ちる思いで読みました。本書は日本のメーカーに10年以上勤めた後米国に移り金融機関に勤務し、幾つかの異なる職場、働き方、考え方を経験した私にとって未だに曖昧だった「企業」の概念をメタ分析のように昇華してくれました。第2章で提示される枠組み(H、G、S、SV、REモード)は経営者、投資家等の実務家にとっても長期的視点での思考の糧になると思います。第5章には日本企業の失われた10年後の生き残りを懸けた「生みの苦しみ」が見て取れます。蛇足ですが政治の役割、影響については、三権(立法、行政、司法)毎の意味合いについてより深い議論をいつか読んでみたいです。本文185ページと短いですが密度は高いです。
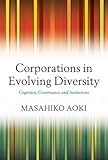
Corporations in Evolving Diversity: Cognition, Governance, and Institutions (Clarendon Lectures in Management Studies)
第1章はAssociational Cognition(連帯認知)のシステムとしての「企業」の導入。第2章ではAssociational Cognition(連帯認知)とOrganizational Architecture(組織構造)、Corporate Governance(企業統治)との関係を整理。第3章では企業活動をゲーム理論を使い政治的・社会的側面から分析し、政治制度の枠組み、社会的規範の役割、また政治・社会・企業間の相互帰還関係について洞察。第4章では社会ゲームのルールの進化について複雑系の視点を再確認。第5章は現在進行中の企業構造の多様化について日本企業の分析を中心に掘り下げています。青木昌彦教授の著書は初めてですが目から鱗が落ちる思いで読みました。本書は日本のメーカーに10年以上勤めた後米国に移り金融機関に勤務し、幾つかの異なる職場、働き方、考え方を経験した私にとって未だに曖昧だった「企業」の概念をメタ分析のように昇華してくれました。第2章で提示される枠組み(H、G、S、SV、REモード)は経営者、投資家等の実務家にとっても長期的視点での思考の糧になると思います。第5章には日本企業の失われた10年後の生き残りを懸けた「生みの苦しみ」が見て取れます。蛇足ですが政治の役割、影響については、三権(立法、行政、司法)毎の意味合いについてより深い議論をいつか読んでみたいです。本文185ページと短いですが密度は高いです。

Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network-theory (Clarendon Lectures in Management Studies)
何でもいいが、ある現象を「社会学的」に説明するとなると、次のようになる。まず、その現象を除いた他の現象の総体を「社会」として括る。そして、その「社会」なるものが原因となって、当該の現象が結果として生じるロジックを構築する。「社会学的説明」とは大雑把に言えばそんな感じである。「社会」が根底にあって、そこから諸現象が帰結として現れる、と。
しかし、そもそも当該の現象それ自体もまた「社会」を構成し、その「社会」をそのような「社会」たらしめているものなのではないのか。だから、当該の現象を切り離したところにある「社会」などありえないのではないのか。たとえば、大英帝国を代表する科学者ケルヴィンが大陸間横断の海底電信ケーブルを作り上げた「原因」は疑いもなく大英帝国という「社会」の要請であったが、同時に、海底電信ケーブルの存在によって大英帝国が大英帝国でありえたのだともいえる。海底電信ケーブルは大英帝国の結果であると同時にその原因でもある。
ある意味、ごくごく当たり前のことを、こんなそれなりに厚い本を書いてまで説明しなきゃいけないという状況が不可解ではありますが、エディンバラ学派が推進した科学知識の社会学の試みによって単純すぎる「社会学的説明」のやり方の限界が露呈したというラトゥールの指摘は当たっていると思う。
デュルケム批判からタルドの再評価へ、といった具合に進む本書は、ラトゥールの本領たるサイエンススタディーズ分野に限らず、広く社会学的研究一般に関心のある人たちに訴える内容になっています。







