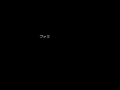坂本龍馬の拳銃
日本のジャズプレーヤーだから、フリージャズ系だから、というような先入観を持たずに聴いていただきたい作品です。聴き始めたら最後まで一気に聴いてしまうでしょう。ドライブ感、爽快感、ピアノの鳴り、それらが一体となって聴き手を圧倒します。
それぞれの曲については、「商品の説明-内容紹介」に全く同感です。ジャズ・スタンダードの1、5、6、10、ミンガスのブルース曲12、いずれもオリジナルの良さを損なわず、見事にスガダイロー作品に仕上がっています。彼自身のコンポーザーとしての実力も確かなものです。我が国のジャズ界にこうした新人が出現したことを素直に喜びたいと思います。

ミンガス・アット・カーネギー・ホール
1974年1月19日、NY、Carnegie Hall。
Charles Mingus Group
Charles Mingus(b)
George Adams(ts) Hamiet Bluiett(bs)
Don Pullen(p) Dannie Richmond(ds)
Guest
Jon Faddis(tp) John Handy(as,ts)
Rahsaan Roland Kirk(ts)
Charles McPherson(as)
これ程暑苦しい演奏はなかなか無い。名演であり、怪演。
当時の Groupに旧友を招いてのJamだが、「ガチンコ、サックス対決」なんです。
吹く小節は好き勝手、順番も決まってない。
で、後にロフト・ジャズのシーンで活躍する、George Adams、Hamiet Bluiettが
霞むくらい凄まじいsoloをとるのが、Roland Kirk様。
「C Jam Blues」では、4番目に出てくるのですが、なんと24chorus吹きまくる。
音は一番でかいわ、お得意の循環呼吸奏法で圧倒。
吹きまくるだけじゃなくて、これでもか、と過去の手練れの有名フレーズを引用。
Coltraneの「至上の愛」が出てきた時には正直笑いましたね。
流石に客受けも凄くて、拍手の量、観客の歓声、めちゃ暑い。
後を受けたJon Faddisもやりにくかったのか、素っ頓狂なフレーズから入って笑える。
「Perdido」では9chorus。真正面から高速バップフレーズを連発の後、
循環呼吸奏法でフリーブロー。もう、笑うしかない強烈さ。
さて、Mingusオヤジはというと、ぶっといウォーキングで全体をがっちり支えております。
この人は、作曲、アレンジも凄いけれど、最高のBassistです。言わずもがな、かな?
笑えて、そして感心する、希有な傑作です。

ミンガス・アット・モンタレイ
“ジャズ語”なるものがあると聞いたことがある。ミュージシャン同士で楽器でしゃべることができるのだという。いってみれば動物同士の会話のようなもので、もし自分にもそんな言葉ができるようになったらいいなと思った。そんなことを考えていたのは20年ぐらい前のことなのだが、そのころ、下北沢のジャズ喫茶「マサコ」でこのアルバムを聴いたときに、それまでにない体験をした。1曲目の「エリントン・メドレー」はミンガスのベースソロによる「アイ・ガット・イット・バッド」から始まるのだが、このとき、ミンガスのソロがまるで私に話しかけているように聴こえてきたのだ。
最初は何か遠くでぶつぶつと小さくつぶやいているような感じだったのが、だんだんその声がハッキリと聴こえるようになり、しまいにはミンガスが何を言いたいのかがわかるような気がしてきたのだ。そのときのミンガスは、まるで自分の惚れた女性に向かって求愛をしているようだった。ロマンティックというよりも、どこか弁解じみているというか、「オレはこんな男でこういう不器用な生き方しかできないんだ」みたいなことを切々と訴えかけているように聴こえてきた。それは、音を言葉に翻訳して理解するというよりも、ダイレクトにその意味が脳に伝わってくる、テレパシーのような感じだった。それがジャズ語を話せるということなのかどうかはまったくわからないのだが、ジャズを
聴いていてそんなふうに感じたのは初めてだった。
このアルバムはミンガスのライブアルバムの中でもよく売れているようだし、たしかにいい出来だ。ただ、これよりもっと素晴らしいミンガス・バンドの演奏はいっぱいある。だが、ここで聴ける彼のベース・ソロは、彼のレコーディング・キャリアの中でもベストではないかと思う。

コーネル1964
Disc One
痛々しいほどに瑞々しく、濃い青空のように新鮮だ。生きることの喜びが湧出するのをミンガスに初めて感じ、涙が出た。各プレヤーの演奏も初々しく、純粋で伸び伸びしている。ミンガス色について言えば、現代文明の持つ退廃と自嘲は、彼の音楽の基調で、彼の社会性の所以であり、怒りのベースになっていると思われるが、ここでは、そうした屈折した感情は表出せず、ひたすらジャズの喜びが進行する。陰性面をしいて挙げれば、孤独が語られている位だろう。観客との掛け合いも楽しげだ。
Disc Two
一気に深くなり、ミンガスの本領発揮で、聴き応えがある。1曲目、現代文明の不安・不条理という呪縛をあるがままに受け止めている男気を感じる。ここに嘲笑はなく、彼は真摯だ。2曲目、雄々しいミンガス、勇気。3曲目、一転して軽快になり、“国歌”ならぬ“地球歌”のようだ。4曲目は楽しげな曲で、地球という宇宙のオアシスに生きることのワクワクするような興、力感を覚える。各プレヤーの力演が素晴らしい。
二枚組みの本作は、フレンドリーなミンガスを心から味わえる名品だ。

Mingus Ah Um
1・6・7・8が1959年5月5日ニューヨーク、残りが1959年5月12日、ニューヨークで録音。5月12日の録音ではジミー・ネッパーに代わりウイリー・デニスが加わっていて残りは同じメンバーである。
このアルバムの裏面には長い長いミンガス自身のコメントが書かれている。そこでは『ジャズ・ワークショップ』のアイデアに始まり、人種隔離反対運動の意思表示も見える。事実このアルバムの中で、差別主義者の白人を徹底的に皮肉った『フォーバス知事の寓話』をやっている。ただそういう意思以上に音楽としてこのアルバムは素晴らしい。後にジョニ・ミッチェルやジェフ・ベックがカヴァーした『グッドバイ・ポーク・パイ・ハット』だけでなく、ブラス・アレンジが光る1や4・5などは後々に登場するジャコ・パストリアスのビッグ・バンドにおけるアレンジに多大な影響を与えていると思う。
このアルバムを支えるサイド・メンは全てミンガス門下生。ミンガスは彼等に譜面を配らず、部分部分を簡単にスケッチしてメンバーに渡し、ピアノで曲の解釈・構成をメンバーに伝える。その後で今度は曲のコードやスケールを説明する。次に一度演奏させ、二度目はミンガスが特別に指定した部分以外はコードやスケールを自由にする。そうやって曲をまとめていったらしい。黒人差別に激しく抵抗したミンガスも音楽では有能であれば人種に関係なく受入れ、お気に入りのトロンボーン、ジミー・ネッパーは白人だったし、2度の結婚も白人だった。
ひとつ笑ってしまうのは当時のライナーを書いている岩浪洋三氏のミンガスの表記があれほどミンガスが嫌がっていた『チャーリー』になっていることだ。『俺をチャーリーと呼ぶな、チャールズと呼べ』というミンガスの罵声が聞こえてくるようだ。